第6回「文芸共和国の会」@広島レヴュー
逆巻しとねです。
思えば前回の広島での会は、カープリーグ優勝の翌日でしたね。人と車がごったがえす市内の狂騒ぶりが昨日のことのように思い起こされます。
さて、今回は、広島市内の中心地に位置する広島経済大学立町キャンパスの一角をお借りして、吉村幸さんによる1940年代フォークナー作品論と萬屋博喜さんによる悲劇のパラドックスをめぐる発表、以上二件の発表と充実した対話を行いました。例によって今回も初参加の方が議論に加わってくださったのは大変心強い限りです。懇親会に至るまで、大変盛り上がりました。広島にはすでにさまざまな分野の研究者がおられることですし、今後ここから派生して市民やこれからの未来を担う若い人たちを巻き込んでいくさまざまな活動が生まれることを期待しています。
以下、当日の発表内容と議論を、わたしの記憶と記録に基づいて再現してみます。
吉村幸さんのご発表「国家と南部に揺らぐ作家の苦悩――1940年代におけるWilliam Faulknerの創作活動の軌跡」は、アメリカン・モダニズムの傑作群として名高い1920年代から30年代にかけてのフォークナー作品から離れ、これまであまり評価されてこなかった1940年代の作品群に描かれた、同時代の時空間と過ぎ去りしヨクナパトゥーファの時空間のあいだに生じる軋轢に文学的価値を認める試みでした。
全4章構成のうち、第1章「南部の変遷とフォークナー」は近代化が進み変貌していく南部のありかたに主眼が置かれていました。まず「熊」においては、文明と荒野とを結ぶ媒介者としての鉄道の役割の変容を音風景の変化、特に音の「響き」に読みとる。次に「主のための柿板(こけらいた)」では、ニューディール政策の一環である公共事業WPAに従事して以降「作業単位」という計量化された時間に生きる労働者と太陽の動きに合わせた前近代的な時間に生きる労働者との対照を示した上で、後者が前者へと飲みこまれていくさまを読む。このように第1章は南部人の変容を、音響感覚や時間感覚の標準化という観点から論じるものでした。
第2章「第二次世界大戦とフォークナー」では、愛国主義的との評価を甘受している短篇を例に、国家間の戦争という超国家的事象がアメリカ南部という一地域に与えるインパクトをめぐる考察が展開されました。「ふたりの兵士」論においては、地域に根差した新聞と地域間をつなぎ想像された国民を形成するラジオとのあいだに存する緊張関係と、後者に対するささやかな忌避感を読み取ることによって、愛国主義的な作品という通念に揺さぶりをかける。さらに「朽ち果てさせまじ」論では、人種の違いを超えて戦争に万人を動員しようとした戦時情報局(OWI)や戦争プロパガンダ映画を量産するハリウッドによる同時代アメリカの世論形成の傾向から逆行するかのような、古い南部黒人のステレオタイプ、及び第二次大戦を南北戦争と混同したり西部劇の騎兵隊を南軍と勘違いしたりする時代錯誤を焦点化する。以上のように、第2章は南部的地域性や旧南部の記憶が1940年代アメリカの愛国主義的な風潮と角逐する要素を抉り出し、両短篇に宛がわれる「愛国主義」という通説に疑問符をつけるものでした。
第3章「アメリカ先住民とフォークナー」では、「求愛」(1948)をそれ以前に書かれた先住民ものと比較検討しながら、人種間融和というテーマと東西冷戦期という時代背景との関係を読み解くことに主眼が置かれていました。1930年代に描かれたMokketubbeに代表される先住民の不活発さと比べると、将来の酋長Ikkemotubbeは快活な人物として描かれています。ひとりの女性をめぐって白人Hogganbeckと激しく争ううちにIkkemotubbeとのあいだに育まれる友愛には、その結果だけを見れば、アメリカ南部の人種差別をナチスになぞらえていた冷戦期ソヴィエトのレトリックに対抗する人種融和のアレゴリーが見え隠れするともいえるかもしれません。しかしその競争の内実をみると、子どもの遊戯性が前景化されている。また「これは昔のことである」に始まり、「昔はこんな風だったのだ」で終わる回顧的な語りの姿勢からして、ここに同時代的な政治性を読むよりは、かつての旧南部へのノスタルジアを読み取るほうが正鵠を得ているでしょう。このように、旧南部への郷愁には、冷戦期の政治的プロパガンダから距離をとる効果が窺えるのです。
第4章「黒人とフォークナー」は中短編集『行け、モーセ』並びに『墓地への侵入者』における黒人表象の揺らぎを問題にします。たとえば「黒衣の道化師」において妻を喪い悲しみに暮れる黒人Riderは白人たちに理解されません。ここには白人の黒人に対する「哀れみや理解の欠如」が顕著です。「作者の代弁者」と評されることの多い、どちらかといえば進歩的な思想の持ち主である、表題作「行け、モーセ」に登場する白人弁護士Gavinもまた、孫の救出を懇願する黒人女性が黒人霊歌を歌いだすに及び、黒人の理解に匙を投げたような態度をとります。『墓地への侵入者』にも人種間の障壁は厳然と存在しています。黒人の少年が白人につき従う姿や黒人の体臭の強調はその典型でしょう。加えて、リンチの予兆が描かれるに及んで、『八月の光』との類似は際立ちます。しかし同時に、『墓地への侵入者』ではリンチは現実化しない。フォークナーが後年ヒトラーになぞらえて言及したPercy Grimのような狂信的な人種差別主義者も存在しない。吉村さんはここに、国民的・世界的名声を獲得するに及び、もはや社会の脅威となる人物を描くことのできないフォークナーの姿を認めます。しかし同時に、狂信的なファシスト的扇動者が登場しないにもかかわらず『墓地への侵入者』で生じるモラル・パニックには、全体主義に対するリベラルの忌避よりは、民主主義に内在するポピュリズム昂進の予兆を読みこむほうが正鵠を得ているのかもしれません。

以上のような吉村さんの発表を受けて、参加者どうしの対話は活発に行われました。1920年代から30年代にかけての作品が研究の中心とされるなか、どちらかといえば道徳的で穏当な作品の目立つ1940年代フォークナーにどのような価値基準を与えるのか。実際の1940年代南部はどのようなものだったのか、フィクションとの差異はどの程度のものなのか。歴史的コンテクストのリサーチが一次史料によっておらず、テクストに適用するには妥当性を欠く、恣意的ではないか。過激な描写を控えるようになった背景には、フォークナーの自己検閲というよりは、編集者との関係があるのではないか(質問者のリサーチの経験を踏まえ、丁寧に説明していただきました)。国家や南部の概念規定が曖昧ではないか。当時の社会のコンテクストというのはどのようなものを前提しているのか、そのコンテクストに一貫性はあるのか、第二次大戦や冷戦という文脈を参照するのは適切か、より具体的なコンテクストを突き合わせて考える必要があるのではないか。愛国主義的作品というレッテルからは逃れているのかもしれないが、その一方で作品の性質上、道徳的で穏当、センチメンタルという従来の評価を超えるものが見当たらないのではないか。他方で、駄作との評価を受けている作品に別の評価基準を与えて再評価することには大きな意義がある、という意見もでました。その他、懇親会に至るまで濃密な議論が展開されました。
吉村さんの発表は現在進行形のD論構想であり、説得力を欠く箇所は残っています。それでもフォークナーの1940年代作品群の研究はほぼ未踏の領域であり、モダニストとは異なる新しいフォークナー像を提示しようという意欲に満ちた発表であったと思います。今後、これを機に、より堅固な研究に結実することを願っています。
それでは吉村さんの感想をご覧下さい。
発表を終えて
吉村 幸
本報告ではアメリカ南部作家ウィリアム・フォークナーの1940年代に書かれた作品を、社会のコンテクストおよび作家の伝記等に照らして再評価することを試みた。まず始めにアメリカ南部のイメージを持ってもらうために、映画「風と共に去りぬ」(旧南部のイメージ)「ふたりの兵士」「墓地への侵入者」(新/近南部のイメージ)の予告編(YouTube)を見ていただいた後、フォークナー作品からの引用を適宜参照しつつ要点を押さえる形で報告を進めた。
成果としては、これまでの研究・評価の流れを述べる必要があることや、国家/南部、愛国主義/国家主義/軍国主義等の概念規定をはっきりさせる必要があることなど、フロアの議論により今後の研究の発展の起爆剤となる手掛かりを発見することができた。発表後日にも当日の参加者の方々から暖かいコメントをメールでいただき、同じく研究の切り口を発見することができた。感謝申し上げたい。
本報告第二章「第二次世界大戦とフォークナー」では、プロパガンダに与する作品に見られる作家フォークナーに加えられた圧力が議論の焦点となったように思う。特に本報告第二章第二部「朽ち果てさせまじ」の報告の最後の部分は、愛国主義的な作品であるという評価を打破できていない、というご指摘は大変貴重なものだった。「朽ち果てさせまじ」の愛国主義に反する姿勢は、作品に描かれる旧南部の記憶にすがりつく南部人の表象に表れている。作品末尾の「車輪」の表象は(外国と区別される)「アメリカ」という国家が一つの名称として表されるものではなく、それを支える国民一人一人によって構成されている、その一個人としての個性を忘れてはならないというフォークナーの想いが込められているのだ、という点で愛国心一辺倒ないわゆる愛国主義に反する姿勢を論じているつもりだったが、上記のご指摘にもある通り、そもそも国家(加えて南部)や愛国主義の概念規定が曖昧で、評価を打破できていないことは実感している。今後の研究課題とさせていただきたい。
今後は「フォークナーが公に対して向けていた顔と内なる想いの分離」という1940年代に抱えていた作家の葛藤を念頭に、プロパガンダや編集者、雑誌の出版社等から加えられた圧力が作品をどのように歪めていったのか、それらの圧力にも関わらずフォークナーが作品で描きだしている内なる想い(国家を代表する作家という顔を裏切る描写等)を明らかにしていきたい。研究を進める上でフォークナーの1940年代の作品の面白さを証明し、前期や中期に偏りがちなフォークナー研究に新たな光を与えていきたい。
――――――――――――――――――――――
休憩を挟んで行われた萬屋博喜さんの発表、「悲劇の快」と物語的期待: ヒュームの洞察」は、イギリスの哲学者デイヴィッド・ヒュームの悲劇論をベースにして、悲劇に固有の快をめぐるパラドックスの問題点を整理し、解決に至っていない不十分な論点の克服を『リア王』の哲学的読解によって試みるものでした。
「悲劇の快」のパラドックスとは、すなわち悲しい出来事や辛い場面が出てくるとはいえ、なぜ人はフィクションだとわかっている舞台上の出来事に心を動かされるのか、という古代以来の謎、通称デュボス問題と呼ばれるものです。萬屋さんの発表は、このパラドックスの美学的解決に取り組むものだった、とひとまずまとめることができるでしょう。
ただし、「悲劇」と「快」というタームはそれぞれ慎重な検討を要します。したがって今回は、特定の悲劇が上演される時代やそれを記録する媒体、作家の評価といった要素は除外し、哲学的アプローチから生理学的アプローチまで周到な議論が必要な快の内実も問わないことにしました。このように、フィクションとしての悲劇に内在する快のメカニズムを見極めることに照準を絞ります。
悲劇のパラドックスはさまざまに構成することが可能ですが、今回は、リヴィングストンが定式化したものを出発点にしました。わたしなりの理解で、ざっくりとまとめると次のようになります。
1.悲劇を観て悲しい気持ちになることは予めわかっている。
2.負の情動は避けたいと思うのがふつう。
3.しかしながら観客は、悲劇を喜んだり、おもしろがったりする。
以上のパラドックスは、観劇行為の動機づけをめぐる矛盾、つまり一般的に人間は負の情動を避けたいと考えるのが常なのに、負の情動をわざわざ享受しに悲劇を観に出かけ、あろうことかそこに感動を覚えたりする、という矛盾にかかわっています。このパラドックスを解消するには、どれかひとつの項目を否定する必要があります。萬屋さんは、三つのうち二番目の項目を標的に選びます。つまり、観劇行為の動機づけに矛盾があるのは、ここで「負の情動」とされているものが実は忌避されるものではないからではないか、という方向にパラドックスを解消することを目論むのです。
デイヴィッド・ヒューム晩年の論稿 “Of Tragedy” (1757)の主題は、この悲劇のパラドックスの解消です。議論の背景には、アリストテレス以来のカタルシス説があります。このカタルシス説を展開する上で、デュボスは負の情動を以下のように位置づけています。
(1)人間にとって最大の悩みは「退屈」である。
(2)「退屈」から解き放ってくれるのであれば、それが苦しく悲しい種類の情動であったとしても、無味乾燥な気だるさよりはマシである。
(3)悲劇がもたらす苦しみや悲しみは、現実のできごとに対するものに比べれば、表面的なものにすぎないため、われわれの側で自由にコントロールできる。
負の情動よりも退屈のほうが苦になる。したがって、退屈に苦しむぐらいならば負の情動に転化したほうがよい。それも悲劇であれば所詮はフィクションなのだから、負の情動もコントロールでき、イタキモチイイ快とすることができる、ということです。
フォントネルはこのイタキモチイイ快を、鑑賞者の抱える苦が快に転じる「感情の混合」として説明しました。鑑賞者は、現実世界において感じている鬱屈した思いを、悲劇のような負の情動に満ちたフィクションの鑑賞を通じて吐き出すことができる。このような意味において、「負の情動を避けたいと思うのがふつう」という規定は崩れます。人はカタルシスを求めて自ら悲劇の鑑賞に赴く、というわけです。
しかしヒュームは、リアルの世界で感じているストレスをフィクションの鑑賞によって発散する、という先行者のカタルシス説の過誤を指摘します。それでは悲劇に内在する負の情動が観客にもたらす快について説明していることにならないからです。観客は予め負の情動を抱え、これをフィクション世界に投影しているとするならば、負の情動を抱えていない観客は悲劇を観にいかないということになる。悲劇に固有の快をフィクション内在的に説明するのではなく、ストレスに悩む観客が悲劇の観劇によってカタルシスを得るというふうに片づけてしまうと、解決をフィクションの外部にいる観客の性質に委ねることになってしまうのです。
ヒュームは、悲劇固有の快を考えるためには、その悲劇の表現(depiction)に注目しなければならないと考えました。悲劇の「表現」は内容と形式とに分類できます。表現の「内容」とは、リア王の発狂、コーデリアの死、グロスター卿の自害といった悲劇中のエピソードの表象です。劇を構成するひとつひとつのエピソード、「点々」が悲劇にしか存在しえないのであれば、それは悲劇固有の快の解明に向かう手がかりとなるでしょう。しかしヒュームは照準を悲劇の「形式」のほうに絞ります。これはつまり、劇を構成する「点々」をつないで「線」にする、あるいはそれらを収容する「ハコ」について考える方向です。つまりは、ヒュームは、悲劇的要素の見せ方、レトリックの演出力に悲劇の快の秘密を探ろうとするのです。
結論としてヒュームが悲劇の表現の形式に認めるのは、観衆が物語に寄せる期待が満たされると、認知の喜びによって悲しみや憐みが正の情動に変わる、という効果です。転換説(conversion theory)と呼ばれるこの解釈によれば、悲劇が喚起する負の情動は、物語的期待の成就によって正の情動へと転換することになります。したがって、悲劇のパラドックスを構成する二番目、「負の情動を避けたいと思うのがふつう」という命題は、悲劇に対する物語的期待が満たされる限りにおいて成り立たないことになります。すると観客の期待を満たすレトリカルな操作がもたらす快こそ悲劇固有の快である、ということになるでしょう。
観客の負の情動が正の情動に転換する原因を観客側の心理ではなく悲劇の構造に求めたヒュームの転換説には一定の説得力が認められます。しかし、依然として転換説には不十分な点が残されています。ひとつには、負の情動がそっくりそのまま正の情動に転換するということがありえるのかどうか。萬屋さんは、悲劇に対する物語的期待が成就することによって負の情動は表面上消えるかもしれないが、劇場を出た後もこの忌まわしい感情は内面のどこかに潜伏しているとのではないか、という疑問を投げかけます。次に、ヒュームの転換説が提示する快は、悲劇に固有であると言えるかどうか。というのも、物語的期待を満たしてくれるフィクションを悲劇に限ることはできないからです。たとえばホラー映画も恐怖を感じつつしかし物語に満足することを通じて快を得ることができる。以上をまとめると、ヒュームの議論を徹底するには、(1)悲劇に固有のプロットは何を中心に回るのか? (2)悲劇の物語的期待を動機づけるものは何か? という問いに答えることが不可欠であることになります。
ヒュームの議論を徹底すべく、萬屋さんはシェイクスピア四大悲劇のひとつ『リア王』を例に、悲劇の快をめぐる仮説を提示する方向に進みます。『リア王』の物語に対する文学的解釈は、たとえばリアを飾り立てる「虚飾」が剥奪されていき、最終的に「真実」が発見される願望の物語という解釈や定常性を喪失し混迷の果てに絶望に至るまでを描いた虚無の物語という解釈などさまざまあります。しかし萬屋さんはスタンリー・カヴェル『悲劇の構造』を手がかりに、ヒュームの議論を受け継ぎ『リア王』に内在するレトリカルな操作と物語的期待を剔抉する哲学的解釈を目指します。
リアによるコーデリアに対する憤激をカヴェルは次のように説明しています。リアは無根拠な生を生きざるをえないことを知っている。だからリア王はおためごかしとはいえ生きる根拠になりうる「偽りの愛」が示されることを望んでいたのに、コーデリアは他の姉妹に追従することなく「真実の愛」を示した。リア王にとってコーデリアの真実の愛は、リアの生の無根拠を覆い隠すさまざまな虚飾を引きはがす「懐疑」として働き、その無根拠を開示するように感じられたがゆえに憤激し、コーデリアを追放するのです。
『リア王』の登場人物はすべて≪根拠なき世界をどう生きるか≫という懐疑論の問題に直面し、世界の断念、愛の回避、認知の回避を強いられている。とりわけリアの悲劇とは、侍従や王としての権威、父としての立場を次々と失い、コーデリアの真実の愛という根拠となりうるものさえ、リアの無根拠の生を暴露する懐疑として感じられてしまう点にあるのです。無根拠な生を覆い隠す虚飾が次々と剥落し無根拠が暴かれる、という物語構造こそが『リア王』の悲劇性の根源にあると言えるでしょう。
では、この『リア王』における人間の生の無根拠を開示する物語形式は、(1)悲劇に固有のプロットは何を中心に回るのか? (2)悲劇の物語的期待を動機づけるものは何か? というヒュームの悲劇論が残した課題にどのような回答をもたらすのか。萬屋さんは、以上のようなカヴェルの『リア王』解釈をヒュームの懐疑論に接続し、悲劇に固有の快の定義を試みます。
〔理性と感覚能力に関する〕懐疑論は、けっして根本的に癒されることのない病であり、われわれがそれをどれほど追い払おうとも、またときには完全に免れているように見えようとも、どの瞬間にもわれわれに戻ってこざるをえない病である。
(Hume, D. (1739), A Treatise of Human Nature, 1.4.2.57)
そもそも観客が生きる現実世界は、多かれ少なかれヒュームのいう懐疑の病に侵されている。であるならカヴェルの読解が剔抉した『リア王』の物語形式は、現実を覆い尽くす懐疑の病をフィクションにおいて現実以上に徹底的に追跡・理解するレトリカルな操作として理解することができるでしょう。つまり、ヒュームの悲劇論は
(1) 悲劇のプロットは、根拠なき世界での生き方の、常識ではありえないほど徹底した追跡・理解を中心に回っている
というかたちで深めることができる。懐疑の病のまわりを周る悲劇のプロットは、他の物語ジャンルとは異なり、観客が生きる現実世界と虚構世界とのあいだにレトリカルな渡しをつけ、後者において生の無根拠さを現実ではありえないほど掘り下げる。観客はフィクションを通じて、底なしの現実を覗きこむことになる。現実生活において、無根拠を徹底的に追究することは困難でしょう。しかし悲劇ならばそれができる。ホラーやミステリーにも当てはまってしまうヒュームの転換説を修正し、悲劇のプロットに固有な要素を懐疑の病の中心化として定義することができます。
では、悲劇にしか向けられない観客の物語的期待があるとしたら、物語形式にはどのような動機づけが埋めこまれているのでしょうか。萬屋さんの仮説は
(2) 悲劇においては、「不条理なもの(悲しみ・憐れみの対象としての運命の原因)」が鑑賞者の物語的期待を動機づける機能を果たしている
というものでした。『リア王』のプロットが観客にもたらす悲しみ・憐みという情動にはふつう、その原因となるものがあると想定されます。萬屋さんはこの原因を「不条理なもの」と呼びます。『リア王』は、悲劇の原因となるものを明示しません。原因を特定できない。それは不条理と呼ぶしかない。『リア王』を観劇することによって感じる悲しみや憐みの原因に観客はたどり着けない。悲しみや憐みは解消されないし、別のポジティヴな感情に変わるわけでもない。ヒュームは、悲劇に対する物語的期待が満たされることによって負の情動が快へと転換する「転換説」を唱えました。ここでは物語的期待と負の情動は別々の原理として働いているようにわたしは思います。しかし萬屋さんの分析によれば、『リア王』のプロットに向けられる物語的期待は、観劇中に感じる悲しみや憐みという負の情動の原因に観客がたどり着くことはできない、この不条理の貫徹によって満たされる(とわたしは理解しています)。わたしが萬屋さんの発表を聞いた限りでは、現実に跋扈する懐疑の病をフィクションにおいて追求するプロットとそこから生まれる観衆の憐みや悲しみとが、不条理という一点において閉じた円環を構成するよう構造化された悲劇に、悲劇に固有の快、すなわち悲劇固有の物語的期待の成就は宿る、ということになるでしょうか。
文献学的に誰かの思想を再現するのではなく、先人の思索の不完全な部分を引き継いでより精緻に思考するという方法、そして問いを扱える範囲に限定しその枠組みの中で一定の答えを出すという哲学的手続きの醍醐味が、萬屋さんのご発表には凝縮されていました。門外漢故に少々冗長な回顧になりました。誤解もあると思います。ご指摘いただければ幸いです。
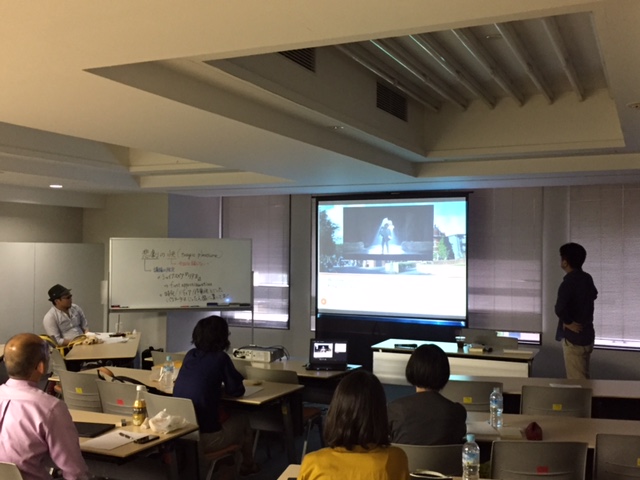
対話は基本的な理解の確認から応用的な解釈まで多岐にわたりました。快のメカニズムについて考察する際に、自然科学による研究も参照されるのか。ニュー・クリティシズムにおける「劇的アイロニー」(「志村、後ろ!」)は悲劇の重要な構成要素と言えないか。悲劇とホラーの差異、不条理と不気味なものは現実と虚構とのあいだの接点を利用するという意味において近いのではないか、すると悲劇固有の物語構造の説明としてはこれでは不十分なのではないか。悲劇の悲劇性はノンフィクションの不幸とも共通するのか(編集やアングルなど形式的なレベルでの操作という点では共通する)。哲学的・美学的読解の特色は何なのか(悲劇というジャンルの特異性を情動的観点から問い直す)。シェイクスピアの悲劇には、異教的なもの、イギリスの外の文化の侵入が色濃く反映されていると考えられ、であるなら懐疑の病を構造化する悲劇の登場には、異教的なものが深くかかわっているのではないか(19世紀に至るまで『リア王』はハッピー・エンドに書き換えられていた)。ではキリスト教に悲劇は存在しないのか(イエスの悲劇があるという意見もありましたが、あれは復活と人類の救済を含みもつため、本発表における悲劇の規定には該当しないと思います)。『ゴドーを待ちながら』のような不条理劇との違いはなにか。悲劇に固有の「快」ではなく、「享楽」の問題として論じると、結末を知っているのにそれでもなお繰り返し悲劇を観劇するリピーターの経験を射程に入れることができるのではないか。その他、多数の意見が出ました。
蛇足ではありますが、エリザベス朝演劇における舞台装置の貧弱さを加味して『リア王』を解釈する必要もあるのかもしれない、とわたしは思います。失明し死を望むグロースターをトム(エドガー)が崖上へと連れて行く有名なシーンがあります。この場面、舞台上は平面であり上り坂などない。エドガーは巧みにグロースターをだましグロースターはこれを信じる。協働作業の結果、グロースターは命を失わずに済む。これはある意味、depictionの形式が内容と一致する場面なのではないかと考えます。つまり、観客は崖の存在を想像力で補いつつも実は崖がないことを知っている、というこの場面の構図は、観客がプロットに期待を重ねると同時にこれが現実ではないことを知っている、という作品全体の形式と一致するのではないでしょうか。ヒュームに倣い、形式面における哲学的考察を展開した萬屋さんの発表は、内容との兼ね合いにおいてより豊かに展開する可能性を秘めていると感じました。
以下、萬屋さんの感想をもって第6回レヴューを終えます。お読みいただき、ありがとうございました。
発表を終えて
萬屋 博喜
まずは、このように貴重な場で発表する機会を与えていただいたことに、心より感謝申し上げます。当日は、できるかぎり専門外の方にも伝わるように話すことを心がけたつもりですが、質疑応答もふくめた活発な反応をいただけたことに内心ホッとしております。
さて、当日の発表では「悲劇の快のパラドクス」という美学上の伝統的問題について、18世紀の哲学者であるデイヴィッド・ヒュームの応答にどれほどの説得力があるのかを検討しました。当初はピーター・ウィアー監督『誓い(Gallipoli)』も扱う予定でしたが、できるだけ議論の道筋をシンプルにするため、当日の発表ではウィリアム・シェイクスピア『リア王』に話の焦点を合わせました。そのことによって、問題の所在がより明確になったのではないかと考えております。
発表の前半では、「悲劇の快のパラドクス」の背景と概要を紹介した上で、「悲劇に固有のプロットへの物語的期待が固有の快を生じさせる」というヒュームの議論(転換説)を検討しました。しかし、ヒュームは何が「悲劇に固有のプロット」であるのかを明確に論じていません。そこで発表の後半では、ヒューム的な転換説の可能性を追究するため、「懐疑論としての悲劇」という論点を強調しているスタンリー・カヴェルの悲劇論を参照しました。その結果として、少なくとも『リア王』については、(1)悲劇に固有のプロットが「生の無根拠さの理解・追跡」を中心とすること、そして(2)「不条理なもの」が悲劇のプロットへの物語的期待への動機づけとして機能することを明らかにしました。
もちろん、以上は『リア王』に特化した議論です。そのため、以上の議論がその他の近代悲劇、あるいは古代悲劇や現代悲劇にも当てはまるのかどうかは、異論の余地があるでしょう。また、今回は演劇というメディアに議論を限定しましたが、映画や小説などの他のメディアについてはどうなのかという点も視野に入れる必要があると思います。
実のところ、文学を主戦場とする方々の前で、(よりにもよって)シェイクスピアの話をしてよいものかどうか悩みました。しかし発表を終えてみれば、多くの方々から文学と哲学の垣根を越えた生産的な反応をいただき、本当に発表してよかったと心から思っております。みなさまにいただいたご批判やご意見をもとにして、今回の主題は継続的に研究を進めていきたいと考えております。今後ともよろしくお願い申し上げます。